NATROM氏はどこで道をあやまったのか〜2002年、ある分岐点〜
承前。http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130718/p1
続々々・NATROM氏『化学物質過敏症は臨床環境医のつくった「医原病」だと思う』等について…なのですが、さすがにくどいのでタイトルを変更しますね。
さて、NATROM氏はAMA(米国医師会)1992年報告書を中心的な根拠としてあげていますが(http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130711#p1)、その2年後、1994年に出ている同会らの報告書には以下の記述があります。
The current consensus is that in cases of claimed or suspected MCS, complaints should not be dismissed as psychogenic, and a thorough workup is essential.
直訳すれば、
『化学物質過敏症であるとの患者の訴えや、その疑いがある場合には、そういった訴えを精神的なものとして却下するのではなく、包括的な検査をすることが不可欠である、というのが現在のコンセンサスである。』
とのようになり、つまりは心因性だので片づけるのではなく、いろいろな方法で包括的に検査しなければいけないよ、ということで、まさに 宮田幹夫氏や坂部貢氏といったいわゆる環境臨床医と呼ばれる方々が取り組んでいる方向性を示しています。
http://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/section/shinryo/allergy/
一方、これまで示したように、NATROM氏の姿勢はこれらAMAの示すところから正反対に向かってしまいました。なぜそうなってしまったのでしょうか?
じつは氏は以下のように、2002年に一度、この文章を取り上げています。
どうも氏はここでなんらかの反論をしたつもりになっているようなのですが、おそらくこの時点で、NATROM氏は致命的なかんちがいをしているようなのです。
氏による訳と解釈をみてみましょう。
The current consensus is that in cases of claimed or suspected MCS, complaints should not be dismissed as psychogenic, and a thorough workup is essential.(多種類化学物質過敏症だと主張されている、あるいは多種類化学物質過敏症だと疑われている症例においては、訴えを精神的なものとし て見過ごされるべきでなく、完全な検査が必要であるというのが、現在のコンセンサスである)
claimed(〜と主張されている)とかsuspected(〜だと疑われている)という表現になっているのに注意してください。そもそも、上記の引用のすぐ上では、
The diagnostic label of multiple chemical sensitivity (MCS) -- also referred to as "chemical hypersensitivity" or "environmental illness" -- is being applied increasingly, although definition of the phenomenon is elusive and its pathogenesis as a distinct entity is not confirmed.(現象の定義がとらえどころがなく、はっきりした実態としての病因が確定されていないのにもかかわらず、「化学物質過敏症」または 「環境病」とも言われる、多種化学物質過敏症(MCS)の診断的ラベルはますます適用されている。)
とあります。要するに、この報告書では、多種化学物質過敏症の定義はとらえどころがなく、多種化学物質過敏症のはっきりとした病因は確定していないとされているのです。「訴えを精神的なものとして見過ごされるべきでない」というのは、「化学物質過敏症」とされている患者の中には、アレルギーなどの身体的な問題をかかえている人も含まれることを言っているに過ぎず、アメリカ肺協会・アメリカ医師会らの報告書は臨床環境医学の主張するような多種化学物質過敏症の概念を支持しているわけではありません。だから、claimed(〜と主張されている)やsuspected(〜だと疑われている)という表現になっているのです。
(http://members.jcom.home.ne.jp/natrom/consensus.html)
どうもNATROM氏は、claimedやsuspectedという単語を用いているから、化学物質過敏症は否定的にとらえられている、といいたいようです。
しかし、claimやsuspectは医学英語において、「患者の病気に関する訴え」「〜という病気の疑い(可能性)」としてごく普通に用いられる単語であって、そこに否定的ニュアンスはありません。
用例:
・HOSPITAL CLAIM FORM (問診票の一種)
https://www.ahsa.com.au/web/freestyler/files/PrivPatientForm%20%28high%20res%29.pdf
・If you suspect you have cancer (がんの疑いがあるならば…)
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/08/get-cancer-checked-out
NATROM氏はこれを知らず、claimedやsuspectedをAMAが化学物質過敏症を否定的にとらえている根拠だとかんちがいしてしまっています。
また、 thorough workupを『完全な検査』と訳しているのも気になる点です。医学的な検査にはノイズや誤差はつきものであって、「完全な検査」という表現は普通もちいられません。この場合は、「包括的な」「徹底的な」といった訳が適切でしょう。
この表現に引きずられてか、あるいはもともと誤って覚えていたのか。flurryさんのエントリ(http://flurry.g.hatena.ne.jp/flurry/20130802)に詳しいですが、NATROM氏は以下のようなかんちがいを表明しています。
定義上、ある診断方法をゴールドスタンダードと定めると、その診断法は感度100%特異度100%の検査だということになります。「その診断方法を基準にしましょう」という意味。
http://twitter.com/NATROM/status/362502353808658434
ここにも大きなかんちがいが二つあります。
1.「ゴールドスタンダード」は標準的な方法や、もっとも広く使われている方法などをあらわす俗語であって、氏のいうような感度や特異度の定義はありません。
gold standard
Term used to describe a method or procedure that is widely recognized as the best available.
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=38019(ステッドマン医学事典)
2.診断法において感度と特異度はトレードオフの関係(一方を上げればもう一方は下がる)にあり、感度100%特異度100%という検査は現実には存在しません。
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0028/G0000070/0091
そして以下のように、NATROM氏は化学物質過敏症診断のゴールドスタンダードは負荷試験であるべき、と考えているようです。
化学物質過敏症の疾患概念を提案した臨床環境医たちは、盲検下負荷試験をゴールドスタンダードにした診断基準に作り直すべきだったのに、そうしなかった。なぜか。
https://twitter.com/NATROM/status/344017019844304897
これらからみえる彼の論理は、まとめるならば
⇒化学物質過敏症診断のゴールドスタンダードは負荷試験
⇒ゴールドスタンダードは感度100%特異度100%
⇒つまり『完全な検査』
⇒『完全な検査』で差が検出できない論文があったから、化学物質過敏症は反証されている
⇒化学物質過敏症は心因性
のようなものであると考えられます。
つまり、かんちがいにかんちがいを重ねた結果、AMAのせっかくの勧告の逆方向に走ってしまったのでしょう。この2002年が、一つの大きな分岐点であったことがうかがえます。この時点でちゃんとこの英文を読んでいれば、軌道修正できたかもしれない。
もちろんここには推測が入っています。が、これまでみてきたようにNATROM氏が多くのかんちがいを重ね、AMAの勧告の反対方向に走り、ゆがめられた情報を広げ、患者に不利益を与え続けていることは現実であり、医学的にも科学的にも大きな問題であるといえます。
NATROM氏は上にあげたAMAの文章をもう一度きちんと読み、なにがまちがっていたのか、ご自身でしっかりと向き合うべきでしょうね。
続々・NATROM氏『化学物質過敏症は臨床環境医のつくった「医原病」だと思う』等について
承前。
http://togetter.com/li/517251
http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130704/p1
http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130712/p1
まず、UpToDateに関して質問がありましたので補足しておきます。
先に述べたように、UpToDateはひとつの参考として有用な情報源ですが、ある疾患に関して、それをみればすべてわかるというような包括的な情報ではないという点が重要です。つまり、化学物質過敏症に関してこういう見解がある、ということは言えても、これが化学物質過敏症に関する一般的で包括的 な見解である、ということはできないわけです。
この点でまず資料の使い方に問題があるといえ、『化学物質過敏症は臨床環境医のつくった医原病』と一般化した氏の発言の根拠として不適切といえます。
http://goo.gl/HdI6L
内容に関しても、こちらのUpToDate記事には米国の臨床環境医の治療が不適切な場合があるとの指摘はありますが、『化学物質過敏症が臨床環境医がつくった医原病』であるとの論証はありません。
ここでは生理的エビデンスの不足を述べていますが、たとえばこちらで免疫システムは関係ない、との根拠にされている文献は1986年および1993年のもの2件のみ、酸化ストレスに関しても1992年1999年の2件のみと、きわめて古く限定的で、近年の多数の免疫学的分子生物学な知見が考慮されているとは到底いえません。こちらの著者(精神科医)は、生命科学の知識に関してはかなり遅れており、偏っていることがわかります。
科学的知見の反映に関して、先に紹介した豪政府レポートの方がはるかに包括的であり、また進んでいるということができます。
また精神的ケアの重要性を述べていますが、それは日本で化学物質過敏症の治療に当たる医師らも述べていることであり、医原病の根拠にはならず、当然顧客が増えればだのなんだのと侮辱する必要はありません。
さらに、ここには
『治療者は精神的症状は最終的には脳神経における生物学的問題であることを留意せよ』
(clinicians should remember that all psychiatric illness is ultimately a disorder of brain biology)、
『化学物質過敏症が心因性であるとの指摘が治療に有益であるかどうかは明らかでない*1』
( it is not clear that the success of psychotherapy depends upon whether patients relinquish their belief that IEI is due to toxic causes.)
とあり、この点からもNATROM氏の発言はなんら正当化されえませんし、むしろ治療の妨害に当たるといえましょう。
せっかくなので水俣病を利用した氏の論点ずらしにも多少つきあっておきましょう。
水俣病と化学物質過敏症は違う疾患なのだから、『水俣病と化学物質過敏症が違う』のは当たり前です。
水俣病には疫学的証拠があったが、化学物質過敏症には不足している、のように氏は書いていますが、なにがいつどの程度あれば十分で、どのくらい不足していれば『医原病』になるというのでしょうか?
水俣病は公式には1956年に認められましたが、50年代初頭にはすでに患者がいたとの証言もあります。劇症型の水俣病はわかりやすかったために比較的早く認定されましたが、わかりにくい軽症型の認定は排除され、胎児性水俣病は調査そのものが行われなかったため、認定がされず、多くの被害者を今も苦しめています。
化学物質過敏症に限らず、状況や症状によっては調査や研究の進展に差が生まれるのは当たり前です。
同じなのは水俣病と化学物質過敏症ではなく、政府や加害企業の公害被害を悪化させる姿勢がNATROM氏と共通している、ということです。
またAMAの1992年(!)時点での見解を上げていますが、現在も多くの議論があるとはいえ、『環境医がつくった医原病である』だのという極論はここからは導かれません。しかもその後も現在にいたるまで化学物質過敏症に関する知見は蓄積し続けており、疾患が否定されるような状況は存在しません。また化学物質過敏症(MCS)という表現も、多くの論文や報告書で使用され続けています。呼称に関しては実際の診療や研究に従事する医師や研究者、患者の間でいずれ合意がとれていくことでしょう。
また、先に書いたように、化学物質過敏症には『疫学的根拠』はあります。氏は杉並病は化学物質過敏症ではないと考える、と根拠もなく書いていますが、これもまた公害問題によく見受けられるご都合主義というしかありません。
では、次のエントリにうつりましょう。
http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130716#p1
まず最初の段落。
また論点ずらしです。いいかげんにしてもらいたいものです。
ホメオパシーの批判はどうぞご自由に、また疑わしい医師がいれば個別に批判すればよろしい。そこから化学物質過敏症や環境医に一般化するのは詭弁としかいいようがありません。
また先に述べたように、特定の実験条件で差が見えないことは、環境条件において超微量の化学物質群一般と関係がないことは意味しません。その条件で検出できない、ということを示すだけです。
ちなみに、二重盲検法で検討して差が検出できた例がないというのも間違いです。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200902130694109899
次からやっと本題に入れそうです。
順に見ていきましょう。
「「化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意によって左右されている」というのは、たとえば、「放射能」を不安に思う人が瓦礫焼却に対して「反応」する一方で、瓦礫受け入れに賛成する人には反応しなかったりすることを指します」
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12764204
さて、氏は上記論文が『化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意』の根拠だといいますが、一部の症状に心理的な影響がある可能性を示唆、ならともかく、『化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意』との強い主張をできるものでは到底ありません。
まず、ここではチェックリストでの質問で『症状』を定義していますが、これが実際の患者の『症状』と同一であるとの検証はしていません。実験における仮の『症状』と、実際の患者の『症状』をそう簡単に同一視してはいけない、というのは医学研究の基礎的な注意点です。二重盲検信仰もそうですが、どうもNATROM氏の言動には、そういった医学研究の実際的な機微が感じられません。
また、そもそも、そういった外部からの条件付けを『恣意』とはいいません。
http://kotobank.jp/word/%E6%81%A3%E6%84%8F
し‐い 【恣意】
自分の思うままに振る舞う心。気ままな考え。「選択は―に任せる」「―的判断」
『恣意』というのは上にあげたように、「思うまま」のようなニュアンスを含むものであり、心理的影響の可能性を示すには不適切であるばかりか、病因を患者に責任転嫁する意味にもなりかねません。患者さんが不快になるのも当然でしょう。
そして心理的影響の可能性は当の環境医がすでに考慮し、ケアしていることは先に示しました。棚上げ?誰が?ということですね。*2
がれき云々の話はそもどれだけの根拠があるのかわかりませんが、たとえば化学物質過敏症の既往や疑いがある方が微量の放射性物質や化学物質を心配するのは当然であるし、またそういう方が微量の放射性物質および化学物質に実際に反応したとして、なんの矛盾もないのだけれど、たったこれだけのことも理解できないのは、氏の思考が『心因性』で凝り固まってしまっているからでしょう。
「臨床環境医たちが厳しい診断基準を作らなかった理由を、「顧客が減るから」だと私は推測する。連中は患者のことなんて考えてないよ。不安を煽って顧客が増えればそれでよかったのだろう」
ここもお話にならないですね。
もちろん原因や機序を探ることは重要でしょう。しかしすでに述べたように、人間の高次機能に関する疾患の研究はきわめて困難であって、遅々とした歩みにならざるを得ません。
しかも水俣病においてもそうでしたが、十分な解明もないままに『厳しい診断基準』を設定することは、いわゆる「非典型例」患者の排除につながり、病因や病態の解明そのものすら阻害しかねません。
またここでも二重盲検信仰というべきまちがいを犯しています。実験条件そのものが確立していない状況で二重盲検で差が出ないということは、環境条件下での化学物質の関与の否定にはなりませんし、プラセボで『実験上の症状』が出ることは、実際の疾患が心因性であることを意味しません。
当然ながら、顧客が減るからだとか、不安を煽って顧客が増えればそれでよかった、などという結論は一切出てきません。
「大事なのは治療?それとも医者の面子?」という言葉はNATROM氏に対してこそふさわしいと私は考えます。
「化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う。」
さて、氏の引用しているデンマークの報告書を見てみましょうか。
確かに、1995年あたりに「医原病モデル」を唱えたグループはいたようですが、現在は2013年です。
そこから蓄積した知見による結論が現在どうなっているか、「原因とメカニズム」のまとめ部分を見てみましょう。
At present, most researchers agree on the following:
1. The mechanism is based on an interaction between one or more physiological and psychological factors and
2. MCS is primarily seen in persons, who react more readily to external environmental impacts than others.The following hypothesis can be put forward: The illness mechanism behind MCS involves both physiological and psychological impacts on certain brain centres in particularly predisposed persons.
現在、ほとんどの研究者は以下の見解に同意している。
1.化学物質過敏症の機序は複数の生理的・心理的要因の相互作用による
2.化学物質過敏症は、外的環境に対して他よりも感受性が高い状態にある個人においてまずみられる
ここから以下の仮説が推奨される:化学物質過敏症における機序には、特に感受性が高くなっている一次曝露を受けた個人の脳の特定部位に対する、生理的心理的双方のインパクトが含まれる。
終了ですね。
追記:デンマークの報告書はこちらに和訳版がありました。
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/mcs_Danish_EPA.html
引用したツイートはもうひとつありますが、そちらの説明はないようです。
https://twitter.com/NATROM/status/343387391605735426
「香り付き柔軟剤で調子が悪くなる人がいるのはよくわかる。しかし、「ドアを開けると放射性物質が入ってくるのが感じられる」とか「3m先の野菜の残留農薬に反応する」とかはわからない。柔軟剤で調子が悪くなる人も、一緒にされたくないでしょ?」
まとめると氏がやっていることは
・その疾患の診断にも治療にも研究にも実際には従事したことのない医師が、
・心理的影響「も」ある、という見解を拡大解釈し、
・実際の患者に対して、偏った考えをもとに干渉し、精神的苦痛を与え、患者間や主治医との分断をうながし、
・これらを指摘されても謝罪もなければ改めることもない
今まさに患者に不利益を与えているのが、ほかならぬNATROM氏本人だといえるでしょう。
どんな分野にもおかしな方はいますから、いわゆる環境医と呼ばれる中にも、おかしな方はいるでしょう。であればその人個人を批判すればよろしい。
ただし、化学物質過敏症に関する氏の姿勢は、自身が「おかしな方」であるといわざるをえません。
氏が本当に医師であるのかどうかは私は知りませんが、少なくとも医師の立場からこういうことを続けるのであれば、大きな問題であるといわざるをえないでしょう。
もう一度書きましょう。
「大事なのは治療?それとも医者の面子?」という言葉はNATROM氏に対してこそふさわしいと私は考えます。
このままの姿勢を続けるのであれば、いずれ患者さん達が断固たる措置をとることもありうるでしょうね。
追記:
ちなみに、NATROM氏は認知療法に関して触れており、化学物質過敏症に対して有意ではないものの、ある程度の有効性が考えられる方法*3も以下のように存在します。
Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: a randomized pilot trial.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22530938/
しかし認知療法といっても、このMindfulness-based cognitive therapyは、化学物質過敏症が化学物質によるとか心因性だとかいった認識の矯正とは異なり、瞑想をメインとする以下のような一種のストレス低減法です。
http://d.hatena.ne.jp/n_n/20110706/p1
マインドフルネスストレス低減法
マインドフルネス認知療法:うつを予防する新しいアプローチ
UpToDateの項に示したように、認識への介入の有効性は明らかではありません。しかし患者のストレス一般を減らすことは大事だということでしょう。別にこれも環境医が否定していることではありませんし、そもこのメソッドが医療現場に入ってきたこと自体が最近のことであって、環境医のせいで遅れたわけではない。
ではNATROM氏の発言は患者のストレスを減らしているか? 否、明らかに増やしています。氏と関わった化学物質過敏症の患者さんに伺えばよろしい。
主治医でも精神科医でもないにも関わらず、医原病や心因性との偏った知識に凝り固まり、治療に意義があるかどうかもわからない認知への介入を行い、患者のストレスを無益に増やしている。
それが氏のやっていることです。そろそろ気づかれてはいかがでしょうか?
*1:直訳だと『心理療法の成果が患者がIEIが物質毒性要因によるものだという考えを廃することによるかは不明である』のような感じ
*2:http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2510dir/n2510_03.htm
*3:In conclusion no significant differences on effect measures were found, which could be a question of power. The positive verbal feedback from the participants in the MBCT group suggests that a larger randomized clinical trial on the effect of MBCT for MCS could be considered.
続・NATROM氏『化学物質過敏症は臨床環境医のつくった「医原病」だと思う』等について
承前。http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130704/p1
さて、先日のエントリにご自身のも含めいくつか反応をいただきました。ところが、それらにはいずれも、きわめて奇妙なある性質が共通しておりました。
なんと、わざわざタイトルにも入れ、リンクもしておいたにもかかわらず、主題である件のまとめにおけるNATROM氏の発言そのものを、誰も論じていないのです!
じつに不思議な現象です。某大阪市長の名が脳裏をよぎりましたが、気のせいでしょう。まあ、そういう姑息なことをなさるのであれば、再度明示しておきましょう。
私が問題にしているのは、こちらのまとめの文脈における、
NATROM氏の主張『化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う』への批判
http://togetter.com/li/517251
以下に代表されるような発言群に関してです。
https://twitter.com/NATROM/status/343369547455270912
「化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意によって左右されている」というのは、たとえば、「放射能」を不安に思う人が瓦礫焼却に対して「反応」する一方で、瓦礫受け入れに賛成する人には反応しなかったりすることを指します。
https://twitter.com/NATROM/status/344017514835095554
臨床環境医たちが厳しい診断基準を作らなかった理由を、「顧客が減るから」だと私は推測する。連中は患者のことなんて考えてないよ。不安を煽って顧客が増えればそれでよかったのだろう。
https://twitter.com/NATROM/status/344020644603764737
化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う。
https://twitter.com/NATROM/status/343387391605735426
香り付き柔軟剤で調子が悪くなる人がいるのはよくわかる。しかし、「ドアを開けると放射性物質が入ってくるのが感じられる」とか「3m先の野菜の残留農薬に反応する」とかはわからない。柔軟剤で調子が悪くなる人も、一緒にされたくないでしょ?
あらためてひどいですね。
これらは化学物質過敏症が多様で不確定だとか、精神症状が含まれるとか、そういうところを大きく踏み越えているのは明白です。
説明なさるのであれば、これら具体的な発言群に対しての具体的な説明をしてください。
ところで、NATROM氏は「臨床医のほとんどが参考にする」、として、UpToDateをあげておられます。
http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130711#p1
もちろん一つの情報として利用するのはよいのですが、これを「確立した知見」だとか、「包括的なレヴュー」としてみるのは大きなまちがいなので、読者諸氏には十分ご注意されたいと思います。
http://blog.goo.ne.jp/druchino/e/8fef82753f90fb761be1e5cb1917e57e
・UpToDate(的なもの)
病気Xについて、いくつかの根拠を提示して、言いきっている。
ただし、執筆者は一人(か少数)のため、個人の意見が強く反映される。
こちらにあるように、情報源にはUpToDate、Narrative review、Systematic review、ガイドラインなど、いろいろな種類がありますが、その中でもUpToDateはもっとも包括度を欠いたもので、基本的には「ある分野のある医師の見解」を紹介したものです。
個々の事実関係に関してまちがいと決めつける必要はないですが、情報の選択およびディスカッションにおいては、個人のバイアスが最も強い情報源として考えましょう。ひとつの立場として参考にするのはかまいませんが、鵜呑みにしていいものではありません。
紹介のUpToDateは精神科医が書いたもののようですから、その精神科医の立場をあらわしたものではありますが、包括度やバランス、バイアスの排除を考えれば、ひとつのUpToDateよりは豪政府の包括的レポートの方が科学的な情報源としてははるかに信頼がおけるといえましょう。
とはいえ一般論として、化学物質過敏症を軽くみて安易な介入をすべきではない、というのはその通りでしょう。
たとえば、医師の立場で、化学物質過敏症の実際の研究にも診療にも携わっていないにもかかわらず、患者に対しての負荷試験を安易に外野から求めたり、上に見られるような与太を患者に飛ばしたり、医療者としていったいどのように正当化されるのか、ちょっと私には理解できません。
先の豪政府レポートの心理的影響の項のまとめには、このようにあります。
Despite evidence of psychological predispositions and psychiatric comorbidity in MCS, an important question is the extent to which these are the cause or an effect of an individual’s MCS condition. The lack of evidence for a physiological cause for MCS should not be interpreted as indicating support for a primarily psychiatric explanation.
http://www.nicnas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/4946/MCS_Final_Report_Nov_2010_PDF.pdf
化学物質過敏症には精神的影響の傾向や精神的な合併症があるが、重要なのはそれらが原因なのか、結果なのか、という問題である。化学物質過敏症において生理的エビデンスが不足しているということを、心理的な説明が第一であるかのように解釈すべきではない。
実際、いわゆる「臨床環境医」として治療に当たっている宮田幹夫氏自身、精神的な影響や精神的なケアを各所で述べています。しかしそれはたとえば、ぜんそく患者が映画のぜんそくのシーンをみて苦しくなってしまうように、ある過敏症を持った患者が、そのつらい発作の記憶のために、似たような状況や臭いにまで反応してしまうようになる、というようなことであって、「心因性」とはいっても『環境医が金のために不安を煽って〜』のような類とはまったく異なります。
http://www.motheru.jp/kakeru03.html
NATROM氏の発言群は、患者をそういったまともなケアから遠ざけるものです。
NATROM氏はツイッター上で実際の患者さんともやり取りしているようですが、その患者さんの受けている診断や治療が誤りだというのであれば、具体的にどういう診断や治療が正しいのか伝え、それを自身で行うなり、それができる医師を紹介するなりすべきでしょう。
浅薄な根拠による発言で患者を不快にさせ、差別的に分断させ、主治医や専門的なケアから遠ざけようとする。氏がやっているのはそういうことです。
ドイツでは、化学物質過敏症を精神病とみなすことは差別である、とされているそうですが、氏がやっていることをみれば、これにも十分うなづけます。
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/Germany/mcs_Germany_CSN_Blog.html
また、NATROM氏はご自身の見解は内科学会でも共有されているニュアンスでおっしゃっているようですが、上に書いたように、精神科医の書いたひとつのUpToDateを学会の見解にするようなことはまずありえないでしょうし、実際に日本内科学会に電話したという方もおられて、NATROM氏見解の否定を受け取っているようです。この点に関して私が再度問い合わせてみてもよいですが、ぜひご自身ではっきりさせていただきたいと思います。
http://aoiazuma.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/natrom-3571.html
NATROM氏『化学物質過敏症は臨床環境医のつくった「医原病」だと思う』等について
NATROM氏の主張『化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う』への批判
http://togetter.com/li/517251
筆が滑るということは誰でもあるし、そういう時は基本的には訂正すればいいことだと思いますが、その後の展開をみるつけ、これは単なる「ひとこと」の問題ではなく、難病や公害に対する基本的な姿勢の問題であるとみることができます。それらに向き合う患者や医師、研究者に対する誤解と軽侮に満ちたこれらの発言を放置すると、根本的にあやまった情報を広めることにもなりかねないので、ここで指摘しておきます。
まず勘違いがあるかもしれませんが、疾患概念や病名というものは、研究室で詳細な機序がわかってから初めてつけられる、という類のものではありません。
当たり前ですが、疾患概念に先立って、まず症状や病気や患者があります。多様な症状や病気や患者に対してなんとか対処しようとするとき、共通点を見つ けて、分類し状況を整理しようとするわけです。
概念にしたがって症状があるのではない、まず雑多な症状が先にあるのです。
ですから、一つの概念でなんの取りこぼしもなく病気を表現できるわけではないし、知見の発展につれて変化したり、細分化したりします。
大きくいって、疾患概念には二つの基準があります。病因基準と、外徴基準です。簡単にいえば、前者は病気の原因からつけられる病名、後者は症状からつけられる病名、ということですね。
たとえば『ヒ素中毒』は前者であり、『気管支炎』は後者といえます。とはいっても、すっぱりきれいに切り分けられるものでもなくて、たとえばヒ素中毒も、原因がヒ素と判明して初めて使える概念であって、わかる前には症状で表現するしかないわけです。
その観点でいえば、『化学物質過敏症』は前者『病因基準』にあたるといえます。しかし、その原因である『化学物質』やその機序についてはまだはっきりわかっていません。
であれば不適切な名称か、といえば必ずしもそうではありません。機序はわからなくても、少なくとも疫学的には、『なんらかの化学物質による微量の曝露が原因であろう』と疫学的にとらえられるケースは報告されています。
Chemical sensitivity: pathophysiology or pathopsychology?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642291(総説)
たとえば日本における化学物質過敏症の地域例として知られる杉並病では、区の調査結果から疫学的にはゴミ中継所からの排出物質が原因と考えるのが妥当とされ、公害等調整委員会もそれを認めました。
では詳細な物質や機序がわかるまで、棚上げすべきでしょうか? その姿勢こそ水俣病対策が遅れ被害を広げた原因だと、著書『医学者は公害事件で何をしてきたのか』において、疫学者の津田敏秀氏は述べています(以下引用はこちらの本から)。

- 作者: 津田敏秀
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2004/06/29
- メディア: 単行本
- クリック: 28回
- この商品を含むブログ (17件) を見る
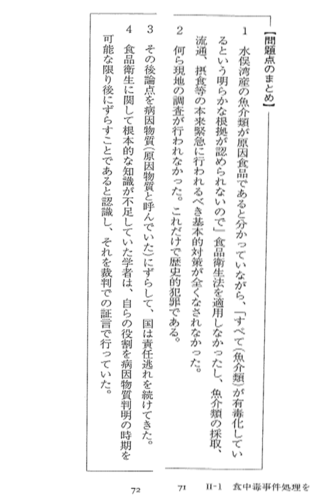
そして先の杉並病でも、疫学的な相関を指摘されながらも、同様に詳細な物質がわからないことを理由に現状維持が図られつづけています。
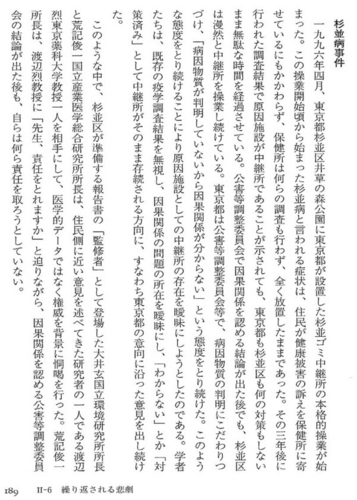
このように、詳細な物質や機序がわからなくとも、なんらかの化学物質への曝露との関連が報告されている以上、『化学物質過敏症』として対策を行うことが不適切だということはできません。
たとえば『金属アレルギー』という概念があります。金属といってもあらゆる金属に反応するわけではありません。金属は人体にもともとたくさん含まれている 成分です。アレルギーといっても金属に対して通常の抗原抗体反応が起こるわけではありません。正確な機序は最近までわからなかったし、現在でも不明な点は 多い。などなど、不正確といえば不正確ですが、ただ不正確というだけでは 不適切な概念とはいえないでしょう。ひとつの概念で病気を表現しきることはできません。『糖尿病』の原因は尿とは直接関係ないし、「糖尿」そのものも副次的な症状にすぎません。糖分のとり過ぎとも直接は関係ない。一型糖尿病と二型糖尿病があり、原因も異なります。
疾病概念は病気に対処するための手段であって、状況によって変化しえます。化学物質過敏症にも本態性環境不耐症という別称があり、こちら が使いやすいのであればこちらを使えばよいでしょうし、よりふさわしい概念があるというならば、根拠と共に提唱すればよいでしょう。
もちろん、疫学的な結果だけではなく、もっと詳細な機序を探ることは大切です。
しかし、公害の多くはそうですが、環境要因の寄与があると思われる、人間の患者自身を使った研究には、多くの制限や困難があります。
神経において器質に大きな損傷を示さなかったり、高次機能に関わる症状の多くは、マウスのような実験動物で検出するのは難しい。発症に時 間がかかったり、慢性的に進行する症状であればなおさらです。
そこで患者自身を対象とした研究、となりますが、まったく当たり前のことですが、患者は実験動物ではありません。
負荷試験と簡単にいいますが、患者に病因となる負荷をかけて実験すること自体、通常では行わない行為です。文字通りの人体実験であって、負荷が大きくな らないよう、最大限の慎重さが求められます。
そういった実験的な負荷試験が、本来の条件を正しく反映しているかどうかはそう簡単にはわからない。
そもそも新たな病気に対しては、どういう検査や試験が適切であるか、ということを検討するところから研究がはじまる。それらが十分確立していな い段階で負荷試験で差が出ない場合があるから心因性、というのは飛躍しすぎです。
また、めまいや頭痛のような、外見的に「非特異的」な症状は、複数の要因で起こりえます。
つまり熱が出たからといって根本的な原因が同一ではないように、末端の症状が同じ、または同じようにみえても、もともとの要因が同じであるとは いえません。
たとえば水俣病関連でも、糖尿病や脳血管疾患の既往があると、症状はそれらのせいであるとして水俣病を否定できるかのような誤った言説がある、 との津田氏による批判があります。これらの「非特異性」によって、非典型例とされた神経症状への認定が行われないことが、今も水俣病患者を苦しめています。

水俣病問題に関する解説的意見書
http://www.okayama-u.ac.jp/user/envepi/dl/13_20120217.pdf
糖尿病や脳血管疾患などは、水俣病と同様あるいは同様にみえる非特異的症状を持つが、それによって水俣病を否定することはできないということです。
したがって、プラセボで「症状」がでることをもって、もともとの「症状」が心因性であるということはできません。
あるいはプラセボでは出ないような、強い条件でたくさんの実験すれば、区別できるかもしれない。しかし再びいいますが、患者は実験動物ではありません。水俣病認定のために、患者に工業排水を飲ませるようなことはありえない。
もちろん、複合的な症状である可能性はあるが、まともな医療においては、心因性というのは最後の可能性として主張されるべきもので、研究途上、 進行中の公害において心因性を安易に持ち出すことの危険性は歴史が示しています。
患者は当然のことながら、実験動物のように規格化されているわけではありません。遺伝的に均一化もされていないし、生活環境もそれぞれ異なります。患者全 体に効くようにと創られた医薬品ですら、患者それぞれの遺伝的生理的バックグラウンドによって効果が異なる、というのは現代では常識です。であ れ ば疾患を引き起こす因子においても同様に患者それぞれのバックグランドが影響します。これらも、個々の実験によって結果がばらつく要因になります。
特に神経の機能に関する影響の検討は、有用な指標やマーカーなどを見つけるところからが課題であり、非常に繊細かつ時間と手間がかかる分野です。
だからといって「反証不能」「研究不能」だ、というのは浅はかです。時間はかかるでしょうが、さまざまなデータが蓄積してくるにつれ、プロトコルは 徐々に改善され、症例のさらなる分類が可能になってくる。研究はそうやって進むものです。
公害のように環境要因の寄与が疑われる病気の場合、歴史上明らかなように、原因物質や機序や条件の検討自体にも時間がかかります。
あらゆる条件 を同時に検討することはできないので、考えられるメカニズムなどから一つ一つ可能性を検討していくしかありません。もちろん要因はひとつであるとも限らないし、 非常に気の長い道のりである。その途上では差が出る条件、出ない条件、複数見解があって当然です。
水俣病は公式発見から60年近く たった現在でも、汚染から発症にいたるまでの正確なメカニズムは明らかではありません。
これらは研究上の困難ではありますが、科学的に反証不可能であるということを意味しないし、対策が取れないことも意味しません。
こういった複雑な事情も含めて、まじめに病気に向き合おうとするなら、たとえば2010年にオーストラリア政府がまとめたレポートが参考になるでしょう。
A SCIENTIFIC REVIEW OF MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY: IDENTIFYING KEY RESEARCH NEEDS.
http://www.nicnas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/4946/MCS_Final_Report_Nov_2010_PDF.pdf
関連する要因として、以下のものが指摘されています。
・Immunological dysregulation
・Respiratory disorder/neurogenic inflammation
・Limbic kindling/neural sensitisation
・NMDA receptor activity and elevated nitric oxide and peroxynitrite
・Toxicant-induced loss oftolerance (TILT)
・Altered xenobiotic metabolism
・Behavioural conditioning .
・Psychological/psychiatric factors
ところで、NATROM氏の「化学物質過敏症は臨床環境医のつくった医原病」というのは病因基準にもとづいた疾患概念の提唱ですね。
病因は「臨床環境医」であり、メカニズムの説明も以下のようになされています。
https://twitter.com/NATROM/status/343369547455270912
「化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意によって左右されている」というのは、たとえば、「放射能」を不安に思う人が瓦礫焼却に対して「反応」する一方で、瓦礫受け入れに賛成する人には反応しなかったりすることを指します。
https://twitter.com/NATROM/status/344017514835095554
臨床環境医たちが厳しい診断基準を作らなかった理由を、「顧客が減るから」だと私は推測する。連中は患者のことなんて考えてないよ。不安を煽って顧客が増えればそれでよかったのだろう。
https://twitter.com/NATROM/status/344020644603764737
化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う。
患者や環境医に対する、きわめて侮蔑的な内容ですが、そういう疾患概念を提唱する自由はあります。
ですが当然、発言の自由は批判される自由でもあり、これほど強い主張を科学の名のもとに公言するのであれば、それなりに根拠を求められます。
たとえば、環境医を曝露要因として検討した疫学研究を示す必要があるでしょう。しかし、どうもそういった研究は見当たりません。
メカニズムに関しては、内心に属するものなので、反証不可能なのが残念なところですね。そういう意図を示した発言記録でもあれば別でしょうが。
また氏のこの見解に対して、以下のような説明をしているところがあります。
http://d.hatena.ne.jp/ublftbo/20130614/p1
みればわかるように、NATROM氏は「医原病」の一般論をしているわけではありません。化学物質過敏症患者および臨床環境医という具体的な対象に対して具体的な見解を述 べ、その具体的な内容が批判されているわけです。
批判されている具体的な内容はスルーして一般論だけ述べ、それが「氏の見解」だとするのは、たとえば特定の歴史的事件に対する特定の見解を批判 されている時に、歴史一般の話にすりかえるような、よくある欺瞞と同様です。
第一、安易な疾病概念の問題を指摘するなら、まずもって「化学物質過敏症は臨床環境医のつくった医原病」という疾病概念についてきちんと批判さ れるべきであるし、不適切だというなら、いつものようになにがどう不適切なのか科学的にきちんと書いてはどうでしょう?
このように疫学は重要ですが、短所もあります。
疫学が威力を発揮するには、大まかな曝露要因がわかっており、発生した症状をきちんと調査していることが 必要です。つまり、被害者が発生してからしか対応できません。また逆に、これらの調査をサボタージュすることによって、「被害の根拠はない」と強弁することもできます。山下俊一氏らとチェルノブイリ調査を行ったことでも知られる重松逸造氏らは、このような疫学の悪用を担っている旨を津田氏は述べています。

さて、現代日本において、重松氏の後を継ぐのは誰でしょうか?
歴史的災害下にあって、巨大な公害被害を繰り返さぬよう、国民は調査や政治に関与する学者の動向を注意深く見ていく必要があるといえるでしょう。
こちらでも同様の問題を指摘しているようです:
似非科学批判と医療の問題について
http://dsj.hatenablog.com/entry/2015/09/06/122750
セシウム137内部被曝のラットモデルによる研究論文紹介
内部被曝に関するもっとも重要な論点のひとつに、化学毒性を生じない、また急性被曝にもいたらないような摂取量(低線量)において、確率的影響以外の生体影響を生じるかどうか、というものがあります。
ここに示した論文はラットを使った、期間も数か月以内の実験ですが、セシウム137を低線量領域において経口投与し、内部被曝させた場合の生理的または分子的影響を調べたものです。
心筋障害マーカーや炎症性サイトカイン、ストレスホルモンの上昇、また、血中ビタミンDや性ホルモンの低下、睡眠覚醒リズムの異常などが認められており、少なくとも、セシウム137低線量内部被曝において、いわゆる化学毒性や確率的影響以外の生体影響が存在することを示しています。これらは、ICRPやUNSCEARにあるような従来のモデルではまったく考慮されていません。
これらの影響が即、病的な状態であるとは限りません。とはいえ、ラットの実験は遺伝的に均質で、健康状態のよい個体を用いて行なっています。
ヒトの場合は遺伝的に多様で、体質や健康状態もそれぞれ異なります。子どもや妊婦も含まれますし、基礎疾患のある場合もあります。また実際の事故被曝では核種もセシウムだけではありません。そのような状況で、内部被曝がどのように健康に影響してくるのか、血液検査等の診断も含め慎重に考える必要があるでしょう。
一番下に、ラット成獣にセシウムを摂取させた場合の各臓器への蓄積を示したグラフをおいておきます。蓄積量から症状を予想するのが難しいことがよくわかります。
たとえば心臓や海馬への蓄積は、臓器の中では特に多いというわけではありませんが、影響が観察されています。臓器や細胞によって機能や応答性が異なるのですから、当たり前といえば当たり前ではありますが。もちろん、これが影響のある最小値かどうかもわかりませんし、他の臓器に影響がないともいえません。
また気になるのは、セシウムが一か月目に甲状腺へ大きく蓄積し、その後は減少に転じている点。従来のモデルでは予想できない動きです。
蓄積メカニズムも、作用メカニズムも、まだまだ謎だらけということでしょう。
Chronic contamination of rats with 137 cesium radionuclide: impact on the cardiovascular system.(ラット慢性内部被曝モデルにおけるセシウム137の心血管系への影響)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18327657
ラットに1日150Bq相当のセシウム137を3か月間投与。血中CK(クレアチンキナーゼ)およびCK-MB(心筋型クレアチンキナーゼ:心筋障害マーカー)が有意に増加。心臓の ACE(アンギオテンシン変換酵素)遺伝子およびBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)遺伝子の発現が有意に増加。心電図ではSTおよびRT部が有意に短縮。血圧が有意に減少、またその日内変動が消失。3か月の内部被曝で心臓の形態に変化はみられなかったが、これらの結果から、セシウム137の低線量内部被曝は、より感受性の高い個体や、より長期の被曝においては、心臓の機能不全につながる可能性が考えられる。
この実験では血中CK-MBが上昇していますが、以下にあるようにこれは代表的な心筋障害マーカーとして知られています。
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0008/G0000020/0006
ちなみに、セシウム内部被曝の心臓への影響に関してはバンダジェフスキー論文がよく知られていますが、これとの関連を論じているところがありましたので参考までに。
Bandazhevskyの心電図データと動物実験との整合性
http://blogs.yahoo.co.jp/geruman_bingo/8557692.html
Chronic contamination with 137Cesium affects Vitamin D3 metabolism in rats.(セシウム137の慢性内部被曝はラットのビタミンD代謝に影響を与える)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16806633
ラットに1日150Bq相当のセシウム137を3か月間投与。肝においてビタミンD代謝に関わるcyp2r1の発現が有意に増加していたが、逆に血中のビタミンD濃度は有意に減少していた。脳ではcyp2r1の発現は減少し、別のビタミンD代謝酵素cyp27b1が増加していた。これらの結果から、セシウム137の低線量内部被曝はビタミンDの代謝系を肝や脳で変化させ、血中のビタミンDを減少させている可能性が示唆される。
ビタミンD欠乏症
日照不足、日光浴不足、過度な紫外線対策、ビタミンD吸収障害、肝障害や腎障害による活性型ビタミンDへの変換が行なわれない場合などに、ビタミンD3が欠乏し、カルシウム、リンの吸収が進まないことによる骨のカルシウム沈着障害が発生し、くる病、骨軟化症、骨粗鬆症が引き起こされることがある。
ビタミンDの不足は、高血圧、結核、癌、歯周病、多発性硬化症、冬季うつ病、末梢動脈疾患、1型糖尿病を含む自己免疫疾患などの疾病への罹患率上昇と関連している可能性が指摘されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3D#.E6.AC.A0.E4.B9.8F.E7.97.87
In vivo effects of chronic contamination with 137 cesium on testicular and adrenal steroidogenesis.(ラット慢性内部被曝モデルにおけるセシウム137の精巣および副腎のステロイド産生への影響)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18046538
ラットに1日150Bq相当のCs137を9か月間投与。血中の17β-estradiol(エストラジオール:性ホルモン)が有意に減少し、corticosterone(ストレスホルモン)が増加していた。精巣では、コレステロール合成に関わるLXRα(肝臓X受容体α)およびLXRβ(肝臓X受容体β)の発現が増加し、FXR(farnesoid X receptor)の発現が減少していた。また副腎では、ホルモン合成に関わるcyp11a1 の発現が減少していた。これらの結果から、Cs137の低線量内部被曝は、性ホルモンやストレスホルモンの分泌や合成に影響を与えることが示唆された。
エストラジオール(エストロゲンの一種)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
http://www.news-medical.net/health/What-does-Estradiol-do-%28Japanese%29.aspx
corticosterone(ストレスホルモンの一種)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%B3
Chronic low dose corticosterone exposure decreased hippocampal cell proliferation, volume and induced anxiety and depression like behaviours in mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18289522
Evaluation of the effect of chronic exposure to 137Cesium on sleep-wake cycle in rats.(セシウム137慢性内部被曝がラットの睡眠覚醒リズムに与える影響の評価)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16876929
ラットに1日200Bq相当のセシウム137を3か月間投与。30日の時点で、開放フィールドでの行動に変化は認められなかったが、覚醒行動や、ノンレム睡眠の頻度が減少し、それらの平均期間が増加した。90日後には、脳のデルタ波(0.5-4 Hz)が増大した。これらの変化は、セシウム137の脳幹への蓄積によって生じている可能性があり、内部被曝の脳機能への影響を、さらに検討する必要がある。
概日リズム障害
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%82%E6%97%A5%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E9%9A%9C%E5%AE%B3
デルタ波
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%BF%E6%B3%A2
Neuro-inflammatory response in rats chronically exposed to (137)Cesium.(セシウム137慢性内部被曝ラットにおける神経炎症反応)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295892
ラットに1日200Bq相当のセシウム137を3か月間投与。海馬において炎症性サイトカインTNFαとIL-6の発現が有意に増加、前頭皮質においてIL-10の発現が有意に増加した。海馬ではTNFαの蛋白質量も増加していた。海馬ではさらに一酸化窒素合成系であるiNOSの発現およびcNOSの活性が有意に増加していた。これらのことから、セシウム137の低線量内部被曝は脳において炎症性サイトカインおよび一酸化窒素シグナルを変化させ、神経における炎症反応を引き起こしていると考えられる。
脳疾患の病理学的シグナル伝達カスケードの頂点に位置する炎症性サイトカイン
http://www.cosmobio.co.jp/aaas_signal/archive/pp-20130115-2.asp
A meta-analysis of cytokines in major depression.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015486
Molecular modifications of cholesterol metabolism in the liver and the brain after chronic contamination with cesium 137.(セシウム137の慢性内部被曝によって肝および脳におけるコレステロール代謝分子が変化する)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19394396
ラットに1日150Bq相当のセシウム137を9か月間投与。コレステロール値自体には有意な変化が認められなかった。一方肝では ACAT2(アセチル基転移酵素2)、Apo E(アポリポ蛋白E)、LXRα(肝臓X受容体α)の遺伝子発現が有意に低下していた。脳では、CYP27A1およびACAT1(アセチル基転移酵素1)の発現が減少していた。これらの結果から、セシウム137の低線量内部被曝は、健康な個体のコレステロール値を直接変化させるほどの影響はなさそうだが、代謝に関わる遺伝子発現を変化させているため、胎児や、代謝性疾患を持っているような、より感受性の高い場合にはより慎重な検討が必要だろう。
ラットに1日200Bq相当のセシウム137を摂取させた場合の各臓器への蓄積
Distribution of 137Cs in rat tissues after various schedules of chronic ingestion.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20539123
より


子どもの甲状腺がんについての総説和訳(抜粋)
まず、311東日本大震災および原発事故関連の被害によって命を落とされた方々に追悼の意を表します。
津波被害に対する補償も十分進まない中、原発事故に関しては事故そのものが収束せず、現在進行中の公害問題であると考えられます。
特に大きな注目を集めたのは被曝による甲状腺がんの発生ですが、現時点で結論を出すことは難しいとはいえ、少なくとも疫学的に見て高い数字であるという意見が津田敏秀氏より出されています。発症率、有病率に関する議論もありますのでぜひご一読を。
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2821.html
ただ、子どもの甲状腺がんに関しては、ネット上にも情報があまりにも少ない。
ツイッターなどで断片的な議論はありますが、まとまった日本語の情報がないため、非常に散漫な印象を受けます。
*1
そこで、2011年に公開された子どもの甲状腺がんに関する英文総説を、特に重要と思われる部分を抜粋して和訳いたしました。
総説の原文はこちら。
Thyroid Carcinoma in Children and Adolescents―Systematic Review of the Literature
無料で読めますので、関心のある方はぜひ原文をどうぞ。
和訳したのは、2. Epidemiology of the Disease 3. Risk Factors 4. Presentation in Childhood 6. Prognosisの各項目です。
*2
小児および青年期における甲状腺がん
疾患の疫学
児童における触知可能な甲状腺結節の頻度は、おそらく1〜1.5%程度と見積もられる*3。しかし、10代以上においては、有病率が13%にも達する場合もある。成人と比べた場合、甲状腺結節と診断された場合のがんリスクは児童では4倍大きい。米国では、毎年20歳以下ではおよそ350人前後が甲状腺がんと診断されている。National Cancer Instituteによると、ブラジルでは、その発症率は小児がんの2%におよぶといわれている。まれな病気であり、分化型甲状腺がんは小児がん全体の0.5〜3%にあたるとされている。
さらに、甲状腺は他の新生物の治療のために頸部に外部放射線治療を受けた子供において、もっともよく二次発がんの起こる箇所の一つである。小児期における甲状腺ガンの発症はきわめてまれである。ただ文献によれば、1歳未満の小児で分化型甲状腺がんが見つかった例もあるという。
また、甲状腺がんの発症率は年齢にしたがって上昇する。Maria Sklodowska記念がんセンターでの235人の小児および少年の甲状腺がん患者のうち、5%は6歳以下で、10%は7-9歳で発見されており、10代以降に大きく増加している。男子と女子の差も13-14歳以降により顕著になってくる。
近年の米国SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results)コホート研究における20歳未満の甲状腺がん患者1753名のデータによれば、女子では10万人当たり0.89人、男子では10万人当たり0.2人の発症率とされる。
リスク要因
過去60年で、児童の甲状腺がん発生率には明瞭な二つのピークがある。
最初のピークは1950年代、頭部白癬、ニキビ、扁桃炎、胸腺過形成など、子どもの様々な治療に放射線を使った時期だ。この時は、被曝後平均10〜20年後に甲状腺ガンが見いだされ、40年間はリスクが続いた。頸部被曝と甲状腺ガンの因果関係が確立され、このような方法が破棄された後、発生率は低下していった。これらのデータにより、放射線が甲状腺がんのリスク要因であると認められるようになった。同様に、他の小児がんに対する外部放射線治療も甲状腺がんの発生率を増加させると考えられる。
次のピークは、1990年代中ごろより、西ヨーロッパ地域にて、1986年のチェルノブイリ原発事故以降に起こった。最初の症例は事故後4-5年後に診断され、特に被曝時に5歳以下だった児童に見いだされた。これらの症例のおよそ75%は出生から14歳までに、25%は14歳から17歳までに、原発事故のフォールアウトによって被曝した。チェルノブイリ事故によって、小児期には成人と比べ、高い放射線感受性があることが明らかとなった。
甲状腺に対する放射線の影響は、科学界の高い関心を集めている。イギリスの小児ガン調査BCCSSは、17980名の小児がん患者に対する、17.4年にわたるコホート研究で、特に二次発がんに注目している。この研究では、甲状腺がんの88%は、頸部に放射線治療を受けた患者に見つかっている。甲状腺がんのリスクはホジキン病および、非ホジキンリンパ腫の治療を受けた患者で高かった。
児童における臨床像
臨床像においては、いくつかの点において小児における病態は成人のものと大きく異なっている。
第一に、20歳以下においては、20〜50歳の患者よりも発見される腫瘍の体積が大きい傾向がある。Zimmermanらは1988年にに、新たに見つかる甲状腺がんは4cm以上が児童では36%に対して成人では15%、1cm未満が児童では9%に対して成人では22%と報告した。乳頭がんの患者のみを考慮すると、診断上は1.5-3%しか1cm未満が見つかっていない。さらに、おそらく児童では甲状腺の体積が小さいためだろうが、カプセル状の被膜や周辺組織の発生が早い。
このように、成人で使われているような微小がん(1cm未満を含む)の分類は、児童においては除外されるべきである。つまり、1cmのがんをこの年齢においては見つけるのはきわめて重要なことだといえる*4。
第二に、児童では多中心性のがんが、特に乳頭がんにおいて多い。これらの多くはポリクローナルながんの発生であると考えられる。このことは、甲状腺ガンの外科的治療における全摘出処置を議論する際に特に重要であろう*5。
第三に、児童の甲状腺がん患者では遠隔転移と同様に、頸部リンパ節への転移の割合が高い。Mayo Clinicにおける1039例の甲状腺乳頭がんにおいては、成人では頸部リンパ節への転移が35%、遠隔転移が2%に対して、児童では頸部リンパ節への転移が90%、遠隔転移が7%であった。われわれが65人の青少年に関して行った調査では、リンパ節への転移は61.5%、局所浸潤は39.5%、遠隔転移(肺転移)は29.2%であった。
診断技術の向上にしたがって、児童における分化型甲状腺ガンの臨床像は変化してきた。ミシガン大学の1970-1990年における診断を、同1936-1970年の診断と比較すると、この何十年かの早期発見技術の進歩を反映し、最近のものの方がリンパ節転移の診断は低く(63%から36%)、局所浸潤も少なく(31%から6%)、肺転移も少ない(19%から6%)。また10年後の予後も改善している。
児童の甲状腺がんの遠隔転移においてもっとも多いのは肺転移であるが、骨転移や中枢神経への転移も少数報告されている。サブタイプの分類は、成人のものと類似している。乳頭がんが90-95%、5%が濾胞がんである。未分化がんはきわめてまれである。
予後
児童の甲状腺がんの予後は非常に興味深いテーマである。成人に比べて高い再発率であるにも関わらず、生存率は成人よりよいようだ*6。MazzaferriとKloosは16.6年の追跡調査により、20歳以上の患者は再発率20%程度であるが、20歳未満の患者の再発率はおよそ40%であることを見いだした。
一方、生存率は成人より高い。ミンスクでの741名のコホート研究によれば、児童の甲状腺がん患者の5年生存率は99.3%、10年生存率は98.5%とされている。
年齢も、甲状腺がんの予後に関してきわめて重要な因子である。小児と青年は通常、ともに比較的よい予後を持ち、45歳以下として分類される。しかし、Lazarらは、10歳未満の、おもに思春期前期の児童は、それ以降の青年期の場合よりも予後が悪いと報告している。
参考:
小児甲状腺がん関連の情報まとめはこちら。
http://matome.naver.jp/odai/2136618062294909201
病理と臨床13年1月号 甲状腺腫瘍の最近のトピックスより
小児甲状腺がんを成人の甲状腺がんの延長で同様に考えることが適切でないことがよくわかります。

http://www.bunkodo.co.jp/byori_52/magazine_detail_4.html
病理解剖データにおける甲状腺がん発見率
病理解剖なので、「病気で亡くなった患者さん(がん含む)」というバイアスがありますが、14歳以下では発見率ゼロです。

http://twitpic.com/c4vcz7
Lancet2003年の甲状腺がんに関する総説の和訳がありました。
http://megalodon.jp/2013-0312-1837-02/www.j-tajiri.or.jp/source/treatise/062/index.html
小児甲状腺がんについては以下。
小児の分化型甲状腺癌
小児の分化型甲状腺癌は稀であり、この疾患に対する適切な治療法についての報告は数少ない。ある研究では*7、小児期に分化型甲状腺癌と診断された患者の25%は再発し、6%は甲状腺癌のために死亡する。頸部放射線外照射の後遺症として、数十年後に気管壊死や頸部肉腫が発生し、3%はそのために死亡する。小児の分化型甲状腺癌は甲状腺内に多発性に癌ができやすいこと、リンパ節転移しやすいこと、遠隔転移を起こしやすいという特徴のために、甲状腺全摘術、頸部リンパ節郭清、術後の放射性ヨード治療を行うことが勧められている。大人になって再発したり、病気が悪化する危険性が高いので、一生涯にわたる経過観察が正当化される。
原文はこちら。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12583960
福島の甲状腺がん関連:
福島の甲状腺検査で過剰診断論が退けられた理由
http://d.hatena.ne.jp/sivad/20150522/p1
長瀧氏やWelchといった過剰診断論者はどこがおかしいのか〜世界や韓国の甲状腺がんの増加に関して〜
http://d.hatena.ne.jp/sivad/20150708/p1
*1:これも含め、小甲状腺がん関連の情報を簡単に以下にまとめました。http://matome.naver.jp/odai/2136618062294909201
*2:なお、被曝による甲状腺がんの臨床像は異なるという意見もありますので、次回は武市宣雄医師による、被曝後に多発した甲状腺がんに関する知見をごく簡単ながらまとめてみようと思います。
*3:無料で読める甲状腺結節に関する総説はこちら。Management of a Solitary Thyroid Nodule http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199302253280807
*4:訳者注:小児甲状腺がんでは見出されるもののほとんどはすでに大きく成長したものであるため、1cm程度のものはその急激な成長途中と考えられ、重要である。
*5:訳者注:多中心性がんは複数のがん細胞が起源となって(ポリクローナル)成長しているがんで、再発率が高い
*6:訳者注:治療後の生存率です。
「黒い雨」被曝者に関する内部資料、通称『オークリッジ・レポート』勝手訳その3
広島において、初期放射線による被曝レベルが低かったとされる範囲内で「黒い雨」に遭遇した生存者については、287名分の文書記録しか残されていない。一方、対照群についても同様に、爆心地から1,600m以上離れた場所にいた生存者が選ばれたが、彼らは観察可能な放射性降雨が確認された周辺地域にはいなかったとという点で「黒い雨」群の生存者とは条件が異なっている。この対照群を構成する生存者は16.045名で、この中には、初期放射線による被曝量が20rad(1rad=10mGy)を上回る例は含まれていない。そのため、作表および分析の対象となったのは、被曝した初期放射線20rad以下の人のみであり、これを「黒い雨」生存者287名に当てはめると236名が該当する。「黒い雨」生存者群が小規模なため、本報告書のいくつかの表のデータは、微粒子沈着と急性被曝症状とを関連付けるには十分ではない。しかし、通常の予測を上回る放射線誘発性の健康異常を訴えた特定の生存者を対象に放射性降下物の研究を行うにあたっては、有効な情報ソースとなる可能性がある。
本調査の「黒い雨」生存者の人数に限りがあるため、次に示すような、当初の仮説を検証することは非常に困難である:
「わずかな放射性降雨によって最初に沈着した微粒子は、その後に降った雨によって生存者の体からすぐに洗い流された。つまり、放射性降雨は二次的な被曝形態であり、放射線損傷を受けたすべての生存者に対してほとんど影響を及ぼすことはなかったと考えられる」。
「黒い雨」群は規模が小さいため、部分群のサイズを最大化するように、放射線症状を分類することが望ましい。ただし、生存者の中には軽微な症状(小症状)を示すもの、顕著な症状(大症状)を示すもの、その両方を示すものが存在するため、こうした作業はそれほど簡単ではない。筆者としては、非対称な部分群同士のデータを結び付けるのではなく、この調査から読み取れる情報は、表10のようなネガティブアプローチによってこそ、よりわかりやすく提示されるものと考える。この表10では、「黒い雨」群(EP)と対照群(CP)それぞれにおいて、主および/または二次的な初期放射線作用に対して観察可能な反応を示さなかったことが報告されている生存者数が比較されている。

さらに、表2〜表7より、「黒い雨」群と対照群の症状発症率の比率を求めることができるが、その結果を表11に示す。

個別の発症比率の値については信頼性の低いものもあるが、全体的には明確な傾向が現れている。中でも、発熱(EPの13.56%)、下痢(EPの22.04%)、脱毛[m](EPの68.64%)の発症比率10、22,15はかなり正確であると考えられる。
[m]:これらの症状を選択した理由としては、その発症率が非常に高く、「黒い雨」生存者のかなり大きな部分母集団を含んでいたことが挙げられる。
嘔吐や非血性下痢はしばしば興奮やストレスによって誘発されることを考慮したとしても、表11に示す症状の発症率からは、「黒い雨」生存者においては顕著な「見込み」ガンマ線被曝量に比べても、ベータ線被曝量がきわめて高かったことが示唆される、と結論づけられるだろう。
謝辞
Y. Okamoto、J. A. Auxier、J. S. Cheka、G. G. Warner の各氏からいただいた貴重な助力と指針に感謝の意を表します。
参考文献
1. Seymour Jablon and Hiroo Kato, Mortality Among A-Bomb Survivors,1950-1970 TR 10-71.
2. G. W. Beebe, T. Yamamoto, Y. S. Matsumoto, and S. E. Gould, ABCC JNIH Pathology Studies, Hiroshima, Nagasaki Report 2, Oct. 1950-Dec. 1965, ABCC TR 8-67.
3. S. Jablon, S. Fujita, K. Fukushima, T. Ishimaru, and J. A. Auxier, "RBE of Neutrons in Japanese Survivors," Proc. Symposium on Neutrons in Radiobiology, Oak Ridge, 1969, USAEC Conf. 69-1106.
4. Shielding Survey and Radiation Dosimetry Study Plan, Hiroshima-Nagasaki, Edited by Kenneth Noble, ABCC TR 7-67.
5. Roy C. Milton and Takao Shohoji, Tentative 1965 Radiation Dose Estimation for Atomic Bomb Survivors, Hiroshima and Nagasaki, ABCC TR 1-68.
6. E. T. Arakawa, Residual Radiation in Hiroshima and Nagasaki, ABCC TR 2-62.
内部配布先:
1-2. Central Research Library 12. H. H. Hubbell, Jr.
3. Document Reference Section 13-32. T. D. Jones
4-6. Laboratory Records Department 33. G. D. Kerr
7. Laboratory Records, ORNL-RC 34. D. R. Nelson
8. ORNL Patent Office 35. W. S. Snyder
9. J. A. Auxier 36. J. B. Storer
10. J. S. Cheka 37. J. R. Totter
11. F.F. Haywood
外部配布先:
38-66. Atomic Bomb Casualty Commission, U. S. Marine Corps Air Station, FPO Seattle, WA 98764. L. R. Allen H. Yamada (10)
G. W. Beebe Epidemiology
G. B. Darling Internal Medicine
S. Jablon Laboratories
H. Maki Library
I. Moriyama Pathology
I. Nagai Radiology
M. Nakaidzumi Shielding Groups (2)
Y. Okamoto (2) Statistics
67. L. J. Deal, Division of Biomedical and Environmental Research, USAEC, Washington, DC 20545.
68. C. L. Dunham, National Academy of Sciences-National Research Council, 2101 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20418.
69. W. T. Ham, Department of Biophysics, Medical College of Virginia, Box 877, Richmond, VA 23319.
70.J. L. Liverman, DBER, USAEC, Washington, DC 20545.
71. C. C. Lushbaugh, ORAU, Oak Ridge, TN 37830.
72. C. W. Mays, Radiobiology Laboratory, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112.
73. K. Z. Morgan, School of Nuclear Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332.
74. H. H. Rossi, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, 630 West 168th Street, New York, NY 10032.
75. Niel Wald, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, R-510 Scaife Hall, Pittsburgh, PA 15213.
76. Shields Warren, Cancer Research Institute, New England Deaconess Hospital, 185 Pilgrim Road, Boston, MA 02114.
77. C. S. White, The Lovelace Foundation, 4800 Gibson Boulevard, SE, Albuquerque, NM 87115.
78. R. W. Wood, DBER, USAEC, Washington, DC 20545.
79. Lowell Woodbury, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112.
80. Research and Technical Support Division, ORO.
81-82. Technical Information Center.
